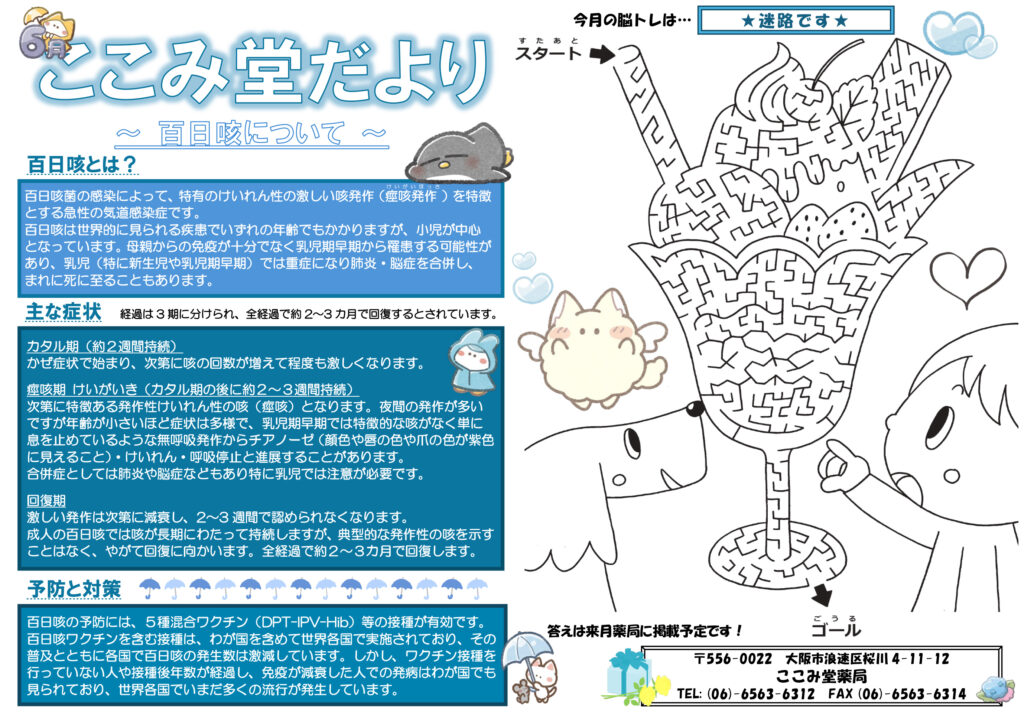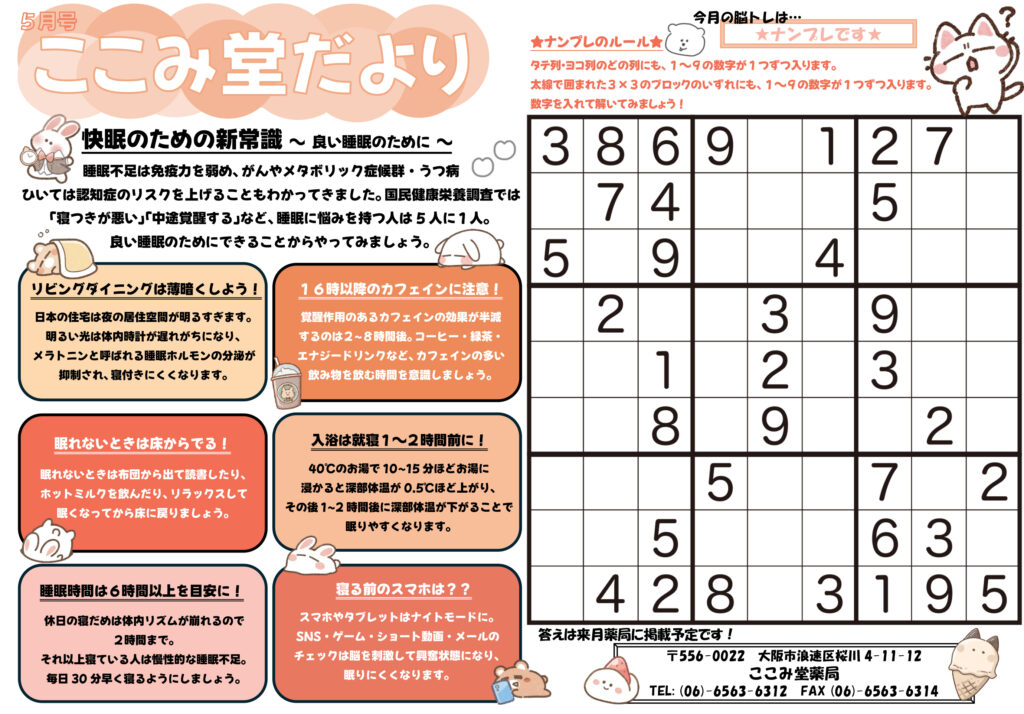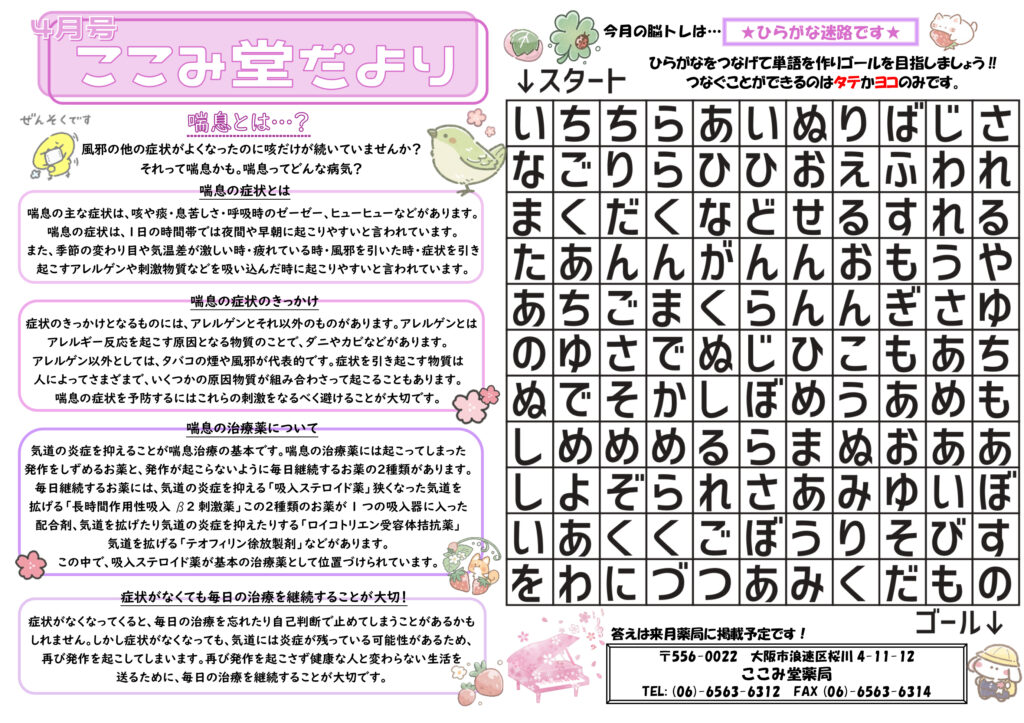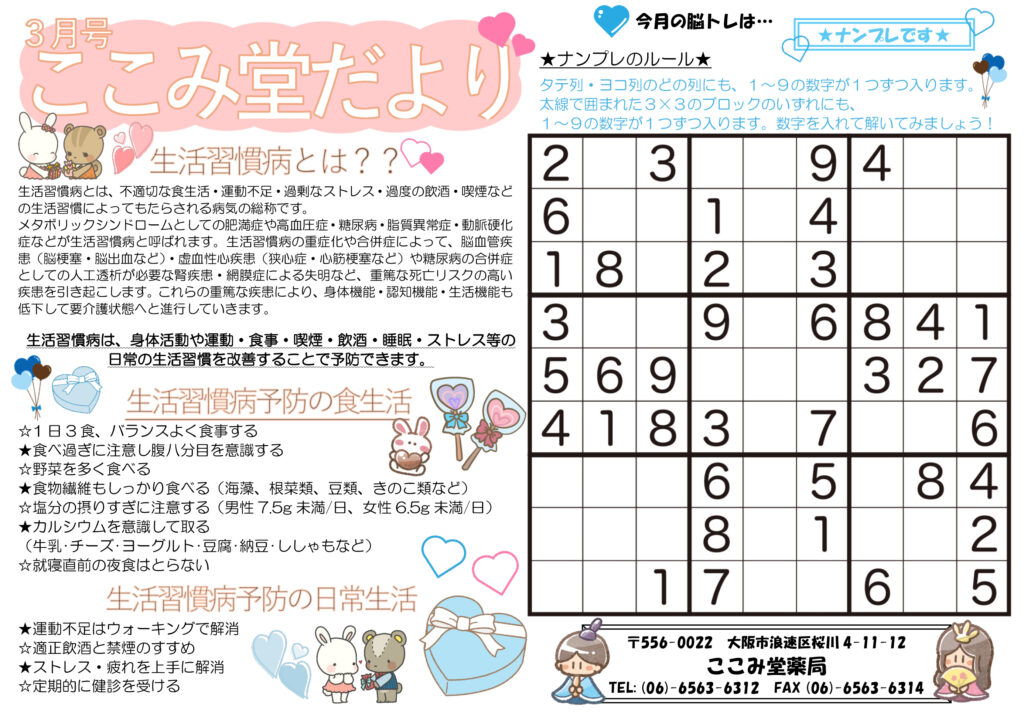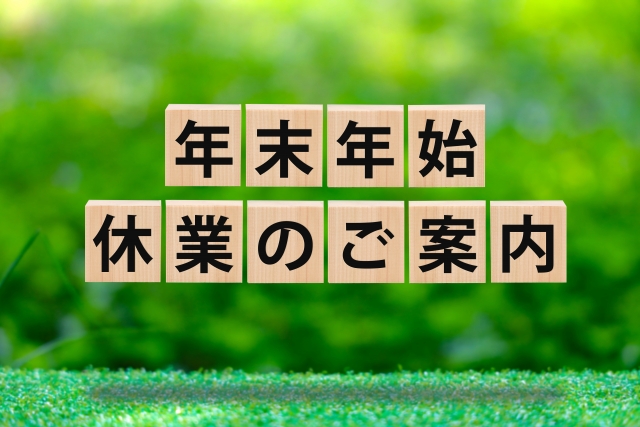~ 百日咳について ~
●百日咳とは?
百日咳菌の感染によって、特有のけいれん性の激しい咳発作(痙咳発作 )を特徴とする急性の気道感染症です。
百日咳は世界的に見られる疾患でいずれの年齢でもかかりますが、小児が中心となっています。母親からの免疫が十分でなく乳児期早期から罹患する可能性があり、乳児(特に新生児や乳児期早期)では重症になり肺炎・脳症を合併し、まれに死に至ることもあります。
●主な症状(経過は3期に分けられ、全経過で約2~3カ月で回復するとされています。)
カタル期(約2週間持続)
かぜ症状で始まり、次第に咳の回数が増えて程度も激しくなります。
痙咳期 けいがいき(カタル期の後に約2~3週間持続)
次第に特徴ある発作性けいれん性の咳(痙咳)となります。夜間の発作が多いですが年齢が小さいほど症状は多様で、乳児期早期では特徴的な咳がなく単に息を止めているような無呼吸発作からチアノーゼ(顔色や唇の色や爪の色が紫色に見えること)・けいれん・呼吸停止と進展することがあります。
合併症としては肺炎や脳症などもあり特に乳児では注意が必要です。
回復期
激しい発作は次第に減衰し、2~3週間で認められなくなります。
成人の百日咳では咳が長期にわたって持続しますが、典型的な発作性の咳を示すことはなく、やがて回復に向かいます。全経過で約2~3カ月で回復します。
●予防と対策
百日咳の予防には、5種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib)等の接種が有効です。
百日咳ワクチンを含む接種は、わが国を含めて世界各国で実施されており、その普及とともに各国で百日咳の発生数は激減しています。しかし、ワクチン接種を行っていない人や接種後年数が経過し、免疫が減衰した人での発病はわが国でも見られており、世界各国でいまだ多くの流行が発生しています。